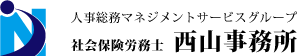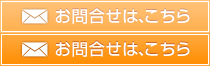Q.改正高年齢者雇用安定法が施行され、希望者全員を継続雇用しなければならなくなりましたが、従業員を定年退職後に再雇用をした場合の年次有給休暇は、新規採用として新たに雇い入れたものとして取り扱えば良いですか。
労働基準法第39条第1項では、「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」。
そして、第2項では、「使用者は、1年6ヶ月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6ヶ月を超えて継続勤務する日(以下「6ヶ月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6ヶ月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6ヶ月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。」と定めています。
年次有給休暇の発生要件は、①当初の6ヶ月間(あるいはその後1年間毎の期間)を継続勤務することと、②対象期間に全労働日の8割以上出勤することです。
定年退職後の再雇用に関しては、①の「継続勤務」か、どうかの解釈がポイントになります。
この「継続勤務」に対する行政通達は次のようになっています。
年次有給休暇の継続勤務に関する行政通達(昭.63.3.14 基発150)
「継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。」
イ.定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合
(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む 。)
ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない。
ロ.法第21条各号に該当する者でも、その実感より見て引き続き使用されていると認められる場合
ハ.臨時工が一定月ごとに労働契約を更新され、6箇月以上に及んでいる場合であって、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
ニ.在籍型の出向をした場合
ホ.休職とされていた者が復職した場合
ヘ. 臨時工、パート等を正規職員に切り替えた場合
ト.会社が解散し、従業員の待遇等を含め、権利義務関係が新会社に包括承継された場合
チ.全員を解雇し、所定の退職金を支給し、その後改めて一部を再採用したが、事業の実体は人員を縮小しただけで、従前とほとんど変わらず事業を継続している場合
定年退職者を嘱託や、契約社員、パート社員等として、新たに労働契約を締結すれば、形式的には別の労働契約ということになります。
しかし、上記の行政通達では、「継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり」とあり、イのような場合「定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合」は、「実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する」としています。
したがって、定年退職者を継続雇用で再雇用した場合においても、年次有給休暇については定年退職前から継続勤務しているものとして取り扱わなければならず、定年時に未消化の年次有給休暇があれば、その権利は引き続き継続します。また、新たな年次有給休暇の発生日が到来すれば、未消化分は翌年度に繰り越されるとともに、過去の勤続年数に応じた年次有給休暇の日数を付与しなければなりません。
一方、上記の行政通達のイでは、「ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない。」としています。退職と再採用との間の期間によっては、継続勤務としてみなされない場合もあります。(※その期間は「○○以上」という具体的な定めがありません。)
しかし、同通達では「継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり」とあり、年次有給休暇の取り扱いを会社に有利にする意図をもって一定の期間の労働契約を保留する措置などは認められず、実態をみて継続雇用と判断される可能性がありますので注意が必要です。